先日、私が
チームビルディングを学んでいる
コミュニティー『チームジャイキリ』の
10周年のイベントがありました。
先日から書いている
熊平さんにお話いただいたのは、
10周年のイベントとしての講演でした。
私はこのこのコミュニティーに
当初から参加しているので
私自身もチームビルディングを学んで
10年になります。
一緒に学び始めたメンバーも
ほぼ10年が経ちました。
最初は、分からないことだらけで、
学ばなければならないことが沢山あって、
学びを得るために
メンバーが集まっていました。
しかし、10年も経つと、
みんな、できることが増えてきて、
仕事も忙しくなってきて、
だんだん集まるのが難しくなってきました。
それが、良い悪いではなく、
そんなものだと思います。
それは、家族も同じだと思っていて、
うちの娘たちも、上の娘は25歳で
社会に出て一人暮らしをしています。
下の娘も22歳で
就活で忙しいのか?家にいません。
家族がそろうなんてことは
めったにありません。
力をつけていけば、
独り立ちするのは健全なことで
悪いことではありません。
生きていく力を身につけて欲しい
と思って育ててきたので、
むしろ、嬉しいことです。
そういう意味で、
「チームジャイキリ」というコミュニティも
メンバー、一人ひとりが、
力を付けて活躍するようになって、
人が集まりづらくなってきたのは、
健全なことだと思います。
こうなることを目指してきました。
しかし、コミュニティーに
人が集まらなくなると
コミュニティーを維持することが
難しくなります。
10周年という区切りを考えた時に
このまま徐々に縮小して
発展的解散をするのか?
さらなる発展を目指すのか?
メンバー、一人ひとりが
考えないといけないタイミングに
来ているのではないか?
という話になりました。
コミュニティーをどうしたら良いか?
それに正解はありません。
メンバー、一人ひとりが
考えなければなりません。
組織というものは、
共通の目的を持った人の集まりです。
共通の目的がなければ、
一緒にいる意味がありません。
ただ、人はやりたいことしかしないから、
その共通の目的が、
メンバーそれぞれがやりたいことに
なっていないと、
その組織に居ようとは思いません。
そう考えると、
あらためて、メンバー、一人ひとりが、
やりたいことが何なのか?を
明確にする必要があります。
メンバーの目的を明確にすることなく
組織の目的を考えたところで、
共通の目的にはなりません。
こんなことを考えていたら、
これって「学習する組織」じゃない?
という話になりました。
「学習する組織」は、
マサチューセッツ工科大学の
ピーター・センゲが生み出した概念です。
学習する組織
システム思考で未来を創造する
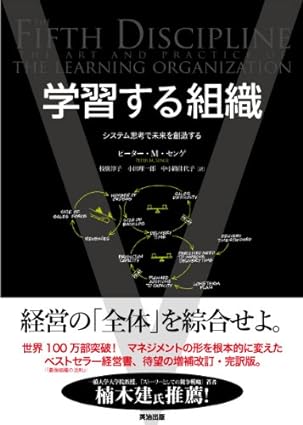
熊平さんが、海外で学んで、
日本で広めようとした概念です。
学習する組織とは・・・
目標に向けて効果的に行動するために
集団としての意識と能力を
継続的に高め、伸ばし続ける組織
と定義づけられています。
チームビルディングのコンサルタントして
こんな組織を作りたい!と思って
コンサルティングしています。
ただ、そうは思っていますが、
現実としては、難しくて、
熊平さんでさえ、
あきらめたとおっしゃっていました。
そんなに難しいのであれば、
我々自身が、
「学習する組織」を目指したらいいじゃない?
と思いました。
では、どうしたら、
「学習する組織」になるのでしょうか?
ピーター・センゲはこんな風に
言っています。
まず、チームのメンバーが、
変革を起こす新しいスキルや
能力を学ぼうとします。新しい能力が育つに連れて、
新しい気付きや感受性も成長します。すると、世の中の見方が変わり、
世の中を体験の仕方が変わるにつれて、
次第に、新しい信念や仮説が生まれ始めます。そして、これが、
スキルや能力のさらなる成長を
可能にします。
こんな風にサイクルが回ることで
学習する「自律した組織」になると言っています。
これを
「チームジャイキリ」というコミュニティー
に当てはめると・・・
石見さんが
世の中にある難解な組織の理論を
分かりやすく、使いやすく
読み解いてくれました。
それによって、
我々、コミュニティーのメンバーは、
新しい能力を身に付け、
新しい気付きを得たり、
感受性を高めることができました。
私が組織のブログを書けるようになったのも
石見さんのお陰です。
それによって、
世の中の見方が変わり、
世の中を体験の仕方が変わるにつれて、
組織を変えることについての
自分なりのやり方や考え方が生まれてきました。
そして、私でだけはなく、
他のメンバーも同じく、
組織を変えることができるようになっています。
そして、そんなメンバーがいるお陰で、
お互いが学び合える組織になってきています。
そんなことを考えていたら、
石見さんは、最初から、
「学習する組織」をイメージして、
コミュニティーづくりをしてきたというのです。
そう言われてみれば、そうなっている・・・
そうなるようにしているから、
そうなっている・・・
最初から石見さんは分かっているのです。
どこまでいっても、
石見さんとの距離は近づきません。
言わなきゃ、わかんないか・・・
と言われてしまいました。
そんなの、一周しないと、
わからないんですよ!
では、「学習する組織」にするために
必要な要素は何なのか?
あらたて考えてみたいと思います。
そう思ったのですが、
長くなったので、
次のブログに書きたいと思います。
今日も最後まで読んでいだき
ありがとうございます。
効き脳コーチングしませんか!
効き脳診断をして、
アナタの「強み」を可視化して
「強み」についてコーチングしませんか?

効き脳診断をしていただき
ZOOMを使って診断結果について
コーチング的にセッションをします。
(約60分間)
効き脳コーチングの詳しいことはコチラ
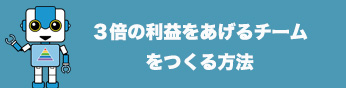








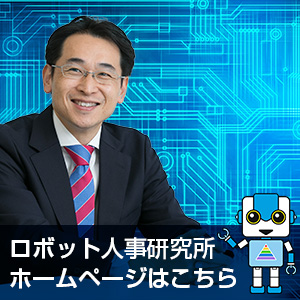
コメントを残す