前回のブログで、
どうしたらいいですか?と質問されたら
その質問には答えないで、
目的と手段の選択基準について
質問をしたらよいという話を書きました。
部下に「考える力」を
身に付けてもらおうとするなら、
上司は質問をすることが必要です。
ただし、上司は質問をすればよい
という話ではありません。
上司の方が部下の方に
質問しているのを聞いていると
上司に答えがあって、
その答えにたどり着くように
質問をしてることが多いように思います。
それは、質問ではなく誘導です。
誘導をしていると、
部下は考えられるようになるのではなく、
誘導されるのが上手くなります。
これの怖いところは、
部下が思い通りの行動をするので、
上司は部下ができるようになった!
と勘違いすることです。
部下は上司の考えていることを
察しているだけで、
考えているわけではありません。
だから、上司の顔色を見ないと
判断ができないということが起こります。
だから、できるようになったと思って
部下に任せた瞬間にできなくなるのです。
というか、そもそも、
できるようになっていないのです。
だから、
誘導されるのが上手くなるための時間って
無駄だと思うのです。
だったら、
最初から誘導することはやめて、
部下に考えさせるようにした方が
よいと思うのです。
そのためにも、
質問をするということなんですが、
以前もブログに書きましたが、
質問には2種類あります。
それは、
自分のためにする質問と
相手のためにする質問です。
部下に考えさせるための質問は、
相手のためにする質問です。
それは、相手(部下)が、
最大の効果を得られるために
必要な情報を明らかにする質問です。
例えば、
部下の視野が狭まっている時に
その視野を広げるための質問だったり、
時間軸を長くするための質問だったり、
可能性を広げるための質問だったり、
相手(部下)がより考えられるような
質問をすることです。
これについては、
GROWモデルという型があって、
先日、このテーマでブログに書いたので、
参考にして下さい。
「成果が上がる面談の仕方」
考えるのは上司ではなく部下です。
上司が一生懸命に考えているようでは、
部下は考えなくなります。
上司が考えなくても、
質問ができるようになるには、
効果的な質問ができるように、
訓練するしかありません。
そう言っている私も
できていないことが多くて
反省することも多いですが、
できるだけ意識をして
質問をするようにしています。
ここら辺、うかうかしていると、
AIの方が上手に面談できるように
なるかもしれません。
若手の育成は、上司でなくて、
AIに任せよう!という時代が
そぐそこまで来ているかもしれません。
この人材育成とAIの問題は、
あまり話題になっていないと思いますが、
大事な問題だと思います。
この問題について
私のチームビルディングの師匠の
石見さんと
「学習する組織」の専門家で
青山学院大学 国際マネジメント研究科
特任教授 熊平美香さんが
3月に対談をします。
「AI時代の人材育成を考える」
https://coachingfarmjapan.com/aifuture
この問題に興味のある方は、
是非、参加していただけれればと思います。
数年先の組織マネジメントを考えるための
ヒントが得られるのではないか?と思います。
今日も最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
|2025年新春 WEBオープンセミナー|
OKRで目標達成できる組織の作り方セミナー

望ましい成果を上げるためには、
チームとして一丸となって、
目標に向かって行くことが必要です。
しかし、目標設定が上手く行かないと
それができなくなります。
目標設定には「やり方」があります。
その「やり方」をワークを通して、
お伝えしたいと思っています。
【日時】
2025年2月20日(木)18時~20時半 満席!
2025年2月27日(木)18時~20時半 満席!
2025年3月4日(火)18時~20時半 残1名
【金額】
5,500円(税込み)
↓
早期割引 3,300円(税込み)
※2025年2月15日まで
セミナーの詳しいことはコチラ
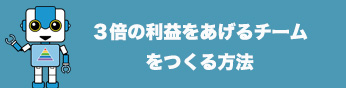


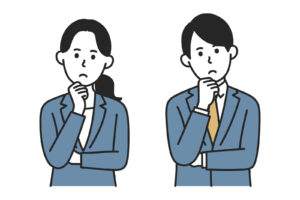
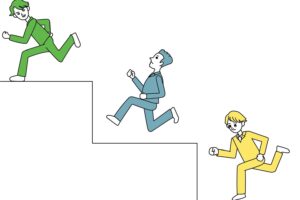






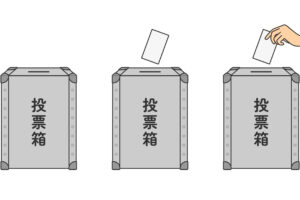



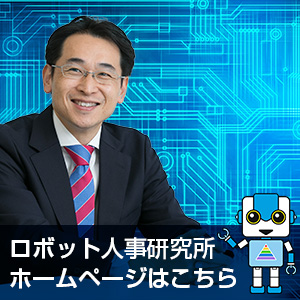
コメントを残す