前回に引き続き、
「識学」について
解説をしたいと思います。
「識学」では5つのステップを経て
行動に移すと考えています。
位置
結果
変化
恐怖
目標
それぞれの段階で
誤解や錯覚が起きていることで
無駄を発生させているといいます。
前回は「結果(責任)」について
解説をしました。
今回は「変化」について
お話をしたいと思います。
世の中に変わらないものは
ないという話をです。
現状維持と言っても
世の中は常に進化しているので、
相対的には衰退しています。
世の中のありとあらゆるものが
変化するのですが、
特に気を付けないといけない
ものがあります。
それは、何でしょうか?

「思考」です。
「思考」は
放っておいても変化しますが、
意図をもってコントロールしないと
何をやっても上手くいかなくなります。
それは、
マザー・テレサの言葉の通りです。
思考に気をつけなさい、
それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、
それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、
それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、
それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい、
それはいつか運命になるから。
つまり、「思考」が人生に
大きな影響を及ぼします。
だから、「思考」は
気を付けなければなりません。

もう1つ、コントロールする
必要があるものがあります。
それは、何でしょうか?
「知識」です。
「知識」は、時に、
行動を阻害する原因になります。
「知識」が増えてきたら、
一旦、止める必要があります。
人が行動できなくなるのは
「知識」がありすぎる時です。
赤ちゃんには
「知識」がないので、
怖いものなしです。
赤ちゃんが
何でも口に物を入れるのは、
喉が詰まって苦しくなることを
知らないからです。
しかし、時間の経過とともに
赤ちゃんは何度か怖い目にあって
「知識」を得ていきます。
物を口に入れたら危ない
という「知識」を「経験」することで
口に物を入れようと思わなくなり
口に物を入れなくなります。

「知識」に「経験」が加わって
「思考」が変化して「行動」が変わります。
これが「成長」です。
つまり、
どんなに「知識」があっても
「経験」をしないと「思考」が変わらず、
「成長」はありません。
当たり前だと思うかもしれませんが、
意外と分かっていない人が
多いのではないか?と思います。
腹落ちしないとやりません!
というのは、このタイプの人です。
しかし、腹落ちは、
やった後でないと起きないのです。
また、部下を納得させるために
とことん話すというのも、
あまり意味がありません。
話して分かるのは「知識」です。
「知識」だけでは
「変化」は起こりません。
「経験」していないからです。

これは、私がいつも言っている
「人はやりながらでないと学べない」
と言っているのと同じことです。
ここでも、
チームビルディングと繋がりました。
そして、さらに
チームビルディング的に考えると
チームが「成長」するというのは、
チームのメンバー全員の
「思考」が変化するということです。
「識学」においては、
メンバーの「思考」が変わる時に
社長が一番やってはいけない
ことがあります。
それは「えこひいき」です。

「えこひいき」をすると
チームメンバーの連動性が失われます。
どういうことか?というと
思考が変化するには
日常の成功や失敗を繰り返しながら
行動をし続けることが必要です。
当然のことですが、
人の成長のスピードは人それぞれです。
それによって、
健全な競争が起こります。
「えこひいき」があると
健全な競争が起きません。
この健全な状態を保つには
不平や不満が出ないことが大切です。
「識学」では、
不平や不満が出ない状態を
どう作るのか?というと
「社員との距離をとる」ことだと
言います。
部下から、不平や不満が出ない
ぐらいの距離感をとることが
大事だというのです。
これは、さすがに
個人的に違和感があります。

私は、社長と話ができることが
この不平や不満が出ない状態を
作るのだと思います。
で、ふと思ったのです。
「識学」と「チームビルディング」
やり方は違っても
目指しているところは
一緒なのだと思いました。
不平や不満が出ない状態を作るために
できるだけ、話を聴こうとするのが
「チームビルディング」
不平や不満が出ない状態を作るために
キリがないので、取り合わないないのが
「識学」
だから、「識学」は、
社長は社長室にこもったほうがいい
というのです。
ここにきて、なんとなく、
「識学」と「チームビルディング」
の違いが説明できるような気がしてきました。
結局のところ、マネジメントは、
社長のパーソナリティーと
ビジネスモデルによるものだと思います。
当たり前のことなんですけど、
ここまで考えると、よく分かります。

「変化」については以上です。
次回は、「恐怖」について
お話をしたいと思います。
今日も最後まで読んでいただき
ありがとうございます。
チームビルディングを学びませんか?
お陰様で、残席2名になりました!
平成30年9月25日(火)品川でやります!
こちらからお申込みができます!
http://robotjinji.com/2018/08/01/post-708/
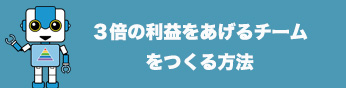
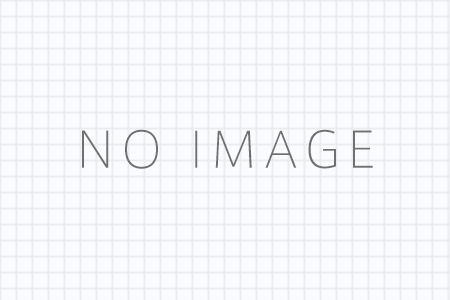
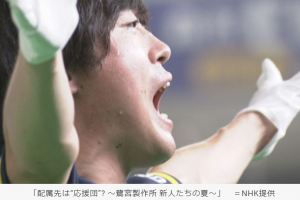

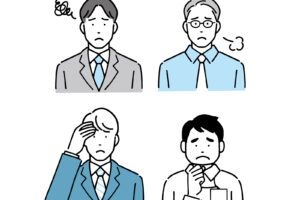



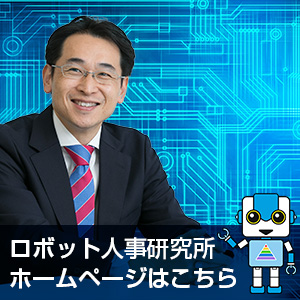
コメントを残す