ここのところ、合宿で学んだことを
書いています。
今回の合宿のテーマは、
メンタルモデルへのアプローチと
アクションラーニング組成方法
についてです。
これまでは、メンタルモデルについて
書いてきましたが、
今回はアクションラーニング組成方法
について書きたいと思います。
メンタルモデルを学んだのも
このアクションラーニングを進めるためです。
アクションラーニングというのは、
学習をしながら問題解決ができるようにする
コンサルティングのスタイルです。
このアクションラーニングを行うのに
大切なことは、
何をテーマにするのか?ということです。
これが正解という方法はないと
思いますが、
今回、学んだ方法は、
ビジネスモデルキャンバスから
テーマを決める方法です。
ビジネスモデルとは、
会社がどのように価値を創造し
顧客に届けるかを論理的かつ
構造的に記述したものです。
ビジネスモデルキャンバスは、
そのビジネスモデルを
事業の構造を9つの要素に分解して
1枚の図で可視化するフレームワークです。
詳しくはこの書籍を参考にして下さい。
図解ビジネスモデル・ジェネレーション ワークショップ
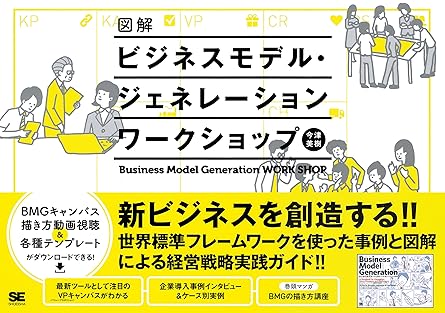
その会社のビジネスモデルを可視化して、
社内の課題と社外の課題を抽出します。
ビジネスモデルキャンバスを見ていると
確かに問題が見えてきます。
提供している価値と顧客のニーズが
ズレていたり、
商品やサービスを提供する手段が
時代に対応できていなかったり、
工場や社屋が老朽化していたり、
主要メンバーが高齢化していたり、
主要取引先が廃業してしまったり、
気になることが見えてきます。
そうしたら、次に、
それぞれについて、起こってほしいことと
起こってほしくないことを考えます。
すると、いくつもテーマが出てきます。
そして、その中から、
取り扱いたいテーマを選びます。
選ぶ基準は、
かける時間、費用に対して、
もっとも、レバレッジが効くものです。
分かりやすくするために、
私がやっている事例を紹介すると・・・
全体の売上目標を達成するとか
買収した会社を立て直すとか
扱っている商品を変えるとか
売上構成比を変えるということを
テーマにしています。
どれも組織を変えることではありますが、
同時に人の成長も必要になります。
つまり、
人と組織の成長を同時に起こすのが
アクションラーニングです。
だから、大事なことは、
アクションラーニングに関わるメンバーが、
自分にとって、
メリットがあると感じられることです。
人はやりたいことしかしません。
でも、人は複雑で、
やりたいと思っても、やるべきだと思っても、
どこかでそれを避けてしまうことがあります。
それが「メンタルモデル」です。
だから、適切に
アクションラーニングを設定するのも
大事なのですが、
同時に、メンバーのメンタルモデルも
扱わないと、
アクションラーニングが進まないのです。
今回の合宿は、
それがテーマだったということです。
私自身、
すでにコンサルティングの中でやっている
ことではありますが、
あらためて、こうして言語化してもらい、
ステップごとに解説をしてもらうと、
再現性が高まります。
あとは、やってみて、
振り返りをして、学習して、
精度を上げていくだけです。
いつも上手く行くとは限りません。
でも、前回も書いたように
いちいち凹んでいる場合ではありません。
上手くいかなかろうが
違和感やモヤモヤを感じようが
とにかくやってみるしかないのです。
今日も最後まで読んでいただいて
ありがとうございます。
効き脳コーチングしませんか!
効き脳診断をして、
アナタの「強み」を可視化して
「強み」についてコーチングしませんか?

効き脳診断をしていただき
ZOOMを使って診断結果について
コーチング的にセッションをします。
(約60分間)
効き脳コーチングの詳しいことはコチラ
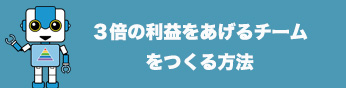


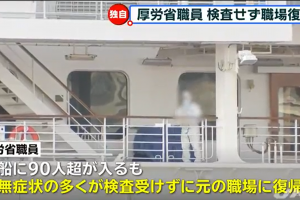











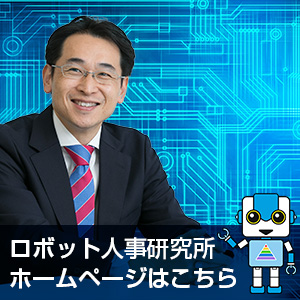
コメントを残す