最近、評価制度を導入したい
という相談をされることが
増えてきました。
ただ、評価制度を導入して
苦労している会社が多いような 気がしています。
本当に導入すべきか? 正直、迷います。
そもそも、評価制度を導入するなら、
最低限できていないと
いけないことがあります。
それは、部下を見ているということです。
こういう話をしていると、
見ていると答える方が多いです。
では、ちょっと、
やってみて欲しいことがあります。
部下の良いところを
3分間でできるだけ書いて下さい!
さて、どれだけ書けましたか?
5個以上の上司は、
部下のことを評価できると思います。
3個以下の上司は、
部下のことを評価できるか?
心配です。
自分のことを見てくれていない上司に
評価をされた部下は、
その評価に納得するでしょうか?
評価制度の内容に
問題もあるかもしれませんが、
どんなによい評価制度を作っても
部下を見ていないことには
評価はできません。
評価制度を作る際に、
設計3割、運用7割なんて
話を聞きます。
しかし、本当にそれでよいのでしょうか?
設計が3割程度の
不完全な評価制度を導入されて、
部下が納得するでしょうか?
3割の評価制度を運用させられる
上司も気の毒だと思います。
そんなことをいっても、
私も10割の評価制度を作ることは
できません。
評価制度で大事なのは、
誰に評価されるか?です。
自分のことをよく見ている人から
評価されたら、納得せざるを得ません。
だから、評価制度を入れる前に
上司が部下を見る仕組みを
導入するべきだと思っています。
その仕組みが1ON1面談です。
それもただ面談をすればよいのではなく、
部下の目標を設定した上で、
その目標達成のための面談に
する必要があります。
何が適切か適切でないかは、
目標によって異なります。
目標がないのに
面談の中で、何を評価してよいのか?
分かりません。
だから、最初に目標設定があり、
面談ができるようになって、
その次に評価制度が来るのだと
思っています。
目標設定もできていないし、
面談もできていない状態で
評価制度を入れてしまうと
それらができるようになるまで
評価制度は機能しないので、
苦労すると思います。
逆の言い方をすると、
目標設定ができていて、
面談ができていれば、
3割の評価制度でも十分機能します。
組織作りには順番があって、
上手く行っていないとしたら、
それは順番の問題かもしれません。
今日も最後まで読んでいただいて
ありがとうございます。
効き脳コーチングしませんか!
効き脳診断をして、
アナタの「強み」を可視化して
「強み」についてコーチングしませんか?

効き脳診断をしていただき
ZOOMを使って診断結果について
コーチング的にセッションをします。
(約60分間)
効き脳コーチングの詳しいことはコチラ
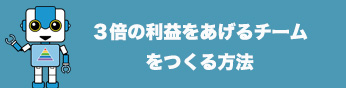



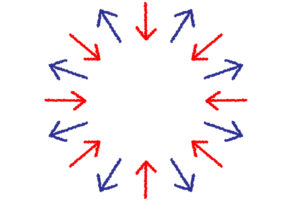
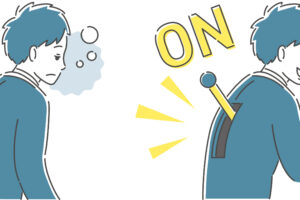




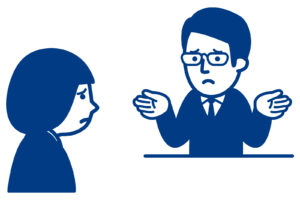
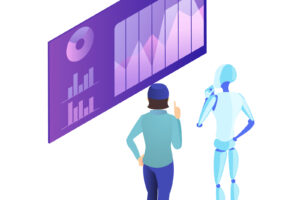
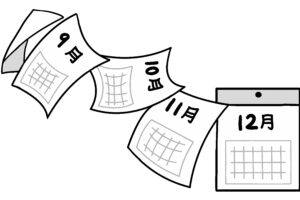


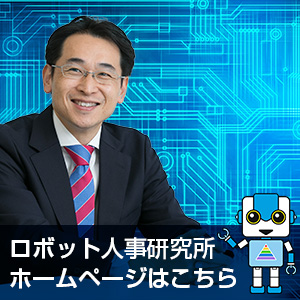
コメントを残す