先日、お客様の会社で
目標設定の話をしました。
目標設定と聞くと
なんだかイヤな気持ちになる人が
多いように思います。
やらされ感というか
プレッシャーというか
重たい雰囲気が漂います。
人はやりたいことしかしないので
そんな重たい雰囲気では、
上手く行かないと思うのです。
私がいつもお伝えしているのは、
目標を達成することに意味がない
ということです。
低い目標を立てれば
簡単に達成ができます。
達成しようと思えば、
低い目標にすればよいのです。
それって意味があるのでしょうか?
わざわざ、
目標を立てる意味がないように思います。
では、なぜ、
目標を立てるのか?というと・・・
目標を達成しようとする時に
あとちょっとで届くという時の力の出し方が
気づきや成長を生むからだと思うのです。
つまり、目標達成をしようとすることに
価値があると思っています。
例えば普通にやっていて、
7ぐらいできる人が
7を目標にしたら7は達成できます。
でも、その人には成長はありません。
できて当たり前です。
しかし、10を目指すとなると、
ちょっと頑張らなければなりません。
普通にやっていて10は行きません。
では、どうするか?というと、
いろいろ工夫してみます。
すると、今までやっていないことを
やってみたりすると、
意外に8とか9まで行きます。
でも、あと「1」が
どうしても足りません。
そこで、めちゃくちゃ考えます。
どうしよう?
どうしよう?
どうしよう?
悩みに悩んで、夢中でやっていると
「1」ができたりします。
その「1」が本当の成長だと思うのです。
この「1」が得られるのは、
ギリギリの中で半ば祈る気持ちで
得られたりします。
人事を尽くして天命を待つ
みたいな・・・
だから、正直、
得られる時と得られない時があります。
でも、それでもよいと思っていて、
その「1」ができなくて9で終わっても、
9の実力があることが分かります。
7だったその人の実力が
9になるのです。
なんだ!9できるじゃん!
ってなります。
それはそれで成長です。
だから、目標達成しなくても
目標を達成しようとすることに
意味はあるのです。
そう考えた時に、
目標の設定の仕方としては、
7ぐらいの人なら、
8か9ぐらいの目標を立てて
プラス1するぐらいが
ちょうど良い目標です。
あまりにも高い目標を立てて
毎回、達成できていないという組織は
自信をなくしているように思います。
自信って自分を信じることなので、
毎回毎回達成できないと
目標を目指すことさえ出来なくなります。
そうなるから
やらされ感というか
プレッシャーというか
重たい雰囲気が漂うのだと思います。
組織には目標が必要で、
目標を達成しようとする意志が
チームを1つにします。
組織が機能していないのは、
目標設定の問題だと思っているのですが
その割には、なんとなく
目標を決める組織が多いように思います。
目標設定は技術なので
意識して学習をしないと
なかなか上達しないのです。
うまく行く組織はますます
うまく行くようになり
上手く行かない組織は
相変わらず上手く行かないのは
そういうことだと思っています。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
効き脳コーチングしませんか!
効き脳診断をして、
アナタの「強み」を可視化して
「強み」についてコーチングしませんか?

効き脳診断をしていただき
ZOOMを使って診断結果について
コーチング的にセッションをします。
(約60分間)
効き脳コーチングの詳しいことはコチラ
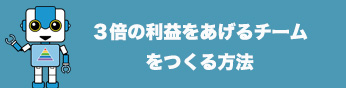







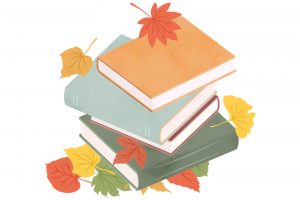
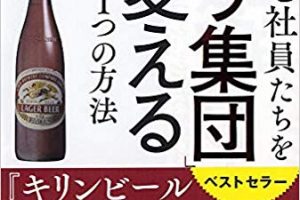





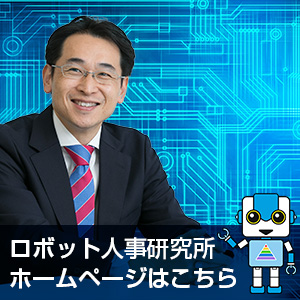
コメントを残す