先日、チームビルディングの勉強会で
これからは、ナレッジマネジメントが
必要になるという話がありました。
ナレッジマネジメントって
聞いたことがあるようなないような・・・
分かっているようで分からない・・・
そこで、調べてみました。
従業員が持つ
知識や経験、ノウハウなどの
「ナレッジ」を
組織全体で共有・活用し、
生産性の向上や
イノベーションの創出を目指す
経営管理手法だそうです。
なるほど…言葉としては
理解できますが、具体的なイメージが
つかめません。
もっと分かりやすい
説明を探してみると・・・
個人の経験や勘といった
言語化しにくい「暗黙知」を
マニュアルや文書などの
「形式知」に変換し、
組織で共有できる形にすることを
目指すものだそうです。
なるほど、これなら分かります。
ベテラン社員の仕事のコツや
職人的な技術を
誰でも再現できるようにすれば、
生産性は確実に上がりますし、
AIやロボットと組み合わせれば、
新しい価値も生み出せそうです。
ただ、
「暗黙知」を「形式知」に変えることは
昔から重要だったはずです。
では、なぜ今になって
ナレッジマネジメントが
これほど注目されるのでしょうか?
その理由を3つあると思います。
1つ目は、世代間ギャップです。
中小企業の現場で感じるのは、
ベテラン社員が若手社員に
仕事を教えることの難しさです。
ベテラン社員と若手社員では、
仕事を学んできた環境がまったく違います。
ベテラン社員は
同期がたくさんいる環境で
働いてきました。
常に競争があり、切磋琢磨しながら
成長してきたのです。
先輩の背中を見て
自ら進んで仕事を覚え、
周りに負けまいと努力しました。
一方、若手社員は
人手不足の時代に入社し、
同期がほとんどいない環境で
働いています。
競争も比較もないため、
マイペースで仕事をこなしてきました。
そのため、
自発的に新しいスキルを
身につけようとする姿勢が
育ちにくいのです。
つまり、学習の道筋を
明確に示さなければ、
成長が止まってしまうのです。
だからこそ、
習得すべき知識やスキルを
体系的にまとめた
マニュアルや文書が必要なのです。
2つ目は、ベテラン社員の教育スキル不足です。
先ほども触れましたが、
ベテラン社員は「見て覚える」という
方法で成長してきました。
体系的に教わった経験がないため、
どう教えればいいのか
分からないのです。
そこで、
教える側も教えやすくなるよう、
知識やノウハウを
文書化しておく必要があるのです。
3つ目は、
若手社員の質問のしづらさです。
ベテラン社員にとって、
今では当たり前のことも
かつては苦労して身につけたはずです。
しかし、その苦労の記憶は
もうほとんど残っていません。
中堅社員がいれば
橋渡し役になれますが、
人手不足の職場では
それも期待できません。
若手社員は、
ちょっとした疑問や不安を
ベテラン社員に聞きづらく、
一人で悩んでしまいます。
そんなとき、
必要な情報が文書化されていれば、
気兼ねなく確認できます。
自分のタイミングで
何度でも見返すことができるのです。
結局のところ、
ベテラン社員が育った時代と
若手社員が働く現在では、
職場環境が大きく変わってしまいました。
若手社員が着実に成長できる
新しい仕組みが必要なのです。
それこそが、ナレッジマネジメント
という考え方だと理解しました。
ただし、
ナレッジマネジメントの実現には
相当な時間と労力が必要です。
本気で取り組む覚悟がなければ、
中途半端に終わってしまう可能性もあります。
会社として明確な意思を持って
組織全体で取り組むことが大事だと思います。
今日も最後まで読んでいただいて
ありがとうございます。
効き脳コーチングしませんか!
効き脳診断をして、
アナタの「強み」を可視化して
「強み」についてコーチングしませんか?

効き脳診断をしていただき
ZOOMを使って診断結果について
コーチング的にセッションをします。
(約60分間)
効き脳コーチングの詳しいことはコチラ
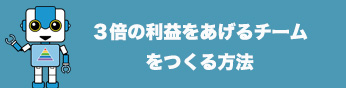

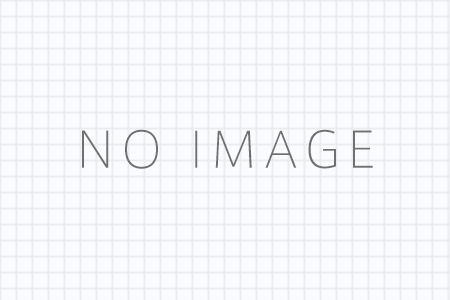



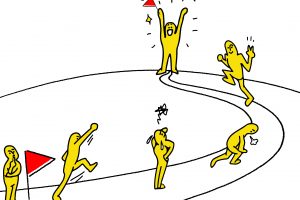








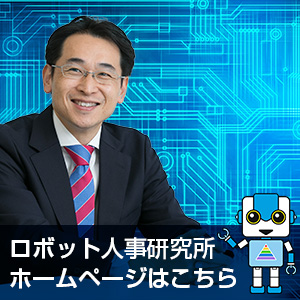
コメントを残す