ネットのニュースを見ていたら
「指導死」という言葉を目にしました。
学校で生徒の指導の行き過ぎで、
子どもの命が失われるという事例が
繰り返されています。
記事によると、
「指導死」の疑いがある事例は、
1989年〜2022年で97件あった
といいます。
残念なことだと思います。
教育現場でも、
指導したら「損」という雰囲気があって、
指導をためらう教員もいるそうです。
そうなると、
指導を受けたこともない若者が
会社に入社してくることになり、
職場でも指導をすることが
難しくなります。
前回のブログでも、
お客様のマネージャーの方から
新入社員の指導について相談を受けた
話を書きました。
指導しないといけないのだけれど
指導したら辞めるんじゃないか……
そんな中、この記事に
解決策になりそうな話があったので
紹介したいと思います。
23年前に指導をした直後、
生徒を亡くした先生のお話です。
この先生は、生徒が亡くなった後、
その生徒のお母さんと対話を続け、
指導の在り方を模索し続けているのだそうです。
その中で、こんなふうにおっしゃっています。
「指導」は「支援」だと考えるようになった。
教師が困ったと思う“困る子”というのは、
きっとこの子は“困っている子”なのだろう
と思うことができるようになった。その子の背景や、その子自身が
どんなふうに感じているかということを、
サポートする中で考えていかないといけない。
「指導」というのは、
正解がある前提でそれを押し付ける
という考え方です。
それに対して、
「支援」というのは、
本人が目指しているものがあって、
それを実現するためにサポートする
という考え方です。
「指導」から「支援」という意識に変わらないと
若者の教育は難しいように感じます。
この意識の変革を現場任せにしている
学校や会社にも問題があると思います。
まさに、指導する人の「支援」が、
学校にも会社にも求められているように
思いました。
今日も最後まで読んでいだき
ありがとうございます。
効き脳コーチングしませんか!
効き脳診断をして、
アナタの「強み」を可視化して
「強み」についてコーチングしませんか?

効き脳診断をしていただき
ZOOMを使って診断結果について
コーチング的にセッションをします。
(約60分間)
効き脳コーチングの詳しいことはコチラ
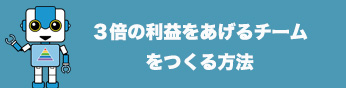









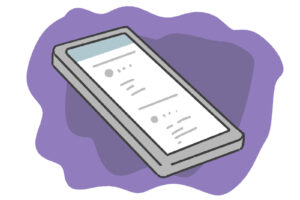


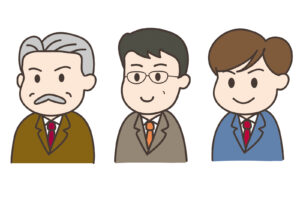

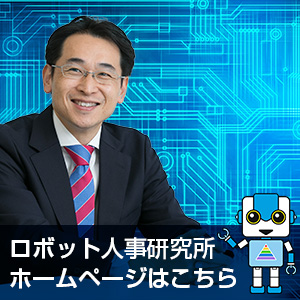
コメントを残す