2025年のノーベル生理学・医学賞に
大阪大学の坂口志文教授が選ばれました。
関節リウマチなどの
“自己免疫疾患”の治療のカギとなる
『制御性T細胞』の発見が評価されました。
個人的には、人間ドックで、
リウマチの数値が高く、経過観察中なので、
いずれお世話になることもあると思います。
それはそれとして、
今回のように、ノーベル賞を取れば、
一躍脚光を浴びますが
それまでは地味な研究をつづけて
こられたのだと思います。
そんな坂口教授へのインタビューで
印象に残ったのは、
座右の銘は?という質問に
四字熟語のような信念はない。
今、自分に言い聞かせるとすれば
「一つ一つ」
とお答えになったことです。
私は組織コンサルタントなので、
医学の事は全く判りませんが、
組織を立て直すのも「1つ1つ」です。
一気に組織を立て直すことはできません。
例えば、課長としての仕事をしていない
という相談を受けたときにどう考えるか?
というと・・・
「課長」という言葉の定義から考えます。
「課長」の役割は何か?
期待されていることは何のか?
それぞれが描いているイメージが
違っていたりします。
このように言葉の定義がずれたまま
話をしていても全く噛み合いません。
まずは、言葉の定義をして、
皆さんの認識を揃えてから、
話し合う必要があります。
おそらく坂口教授の研究も、
このように、いや、これ以上に
細かい作業の積み重だと思います。
なぜこういう細かい積み重ねができるのか?
というと・・・
何か、変だぞ?と思った興味を
失わなかったからだと思います。
「なんらかの制御をするT細胞が存在しないと
免疫反応を説明することができない」
と仮説を立てたことから、
「T細胞」の発見につながったそうです。
組織の問題でいうと、
一人一人は組織を良くしよう
と思っているのに、
組織が上手くいかなのは、何か変だぞ?
と考えるのです。
これを誰が悪い?というように
考えるは簡単です。
しかし、一人一人は、
組織を良くしようと思っているのだから、
そう考えてしまったら、
本当の問題に気付けなくなります。
何かがこの現象を引き起こしているはずだ
と考えるのです。
そうやって考えるから、
一人一人の認識の違いが原因だと
たどり着くことができます。
そして、一人一人の認識の違いを
一つ一つ、対話で乗り越えることが
組織を機能させることにつながります。
それは、一気には解決しません。
一つ一つなんです。
結局は、どんなことでも、
一つ一つ解決していくしかないのではないか?
と思っています。
今日も最後まで読んでいただいて
ありがとうございます。
効き脳コーチングしませんか!
効き脳診断をして、
アナタの「強み」を可視化して
「強み」についてコーチングしませんか?

効き脳診断をしていただき
ZOOMを使って診断結果について
コーチング的にセッションをします。
(約60分間)
効き脳コーチングの詳しいことはコチラ
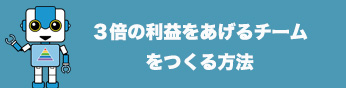
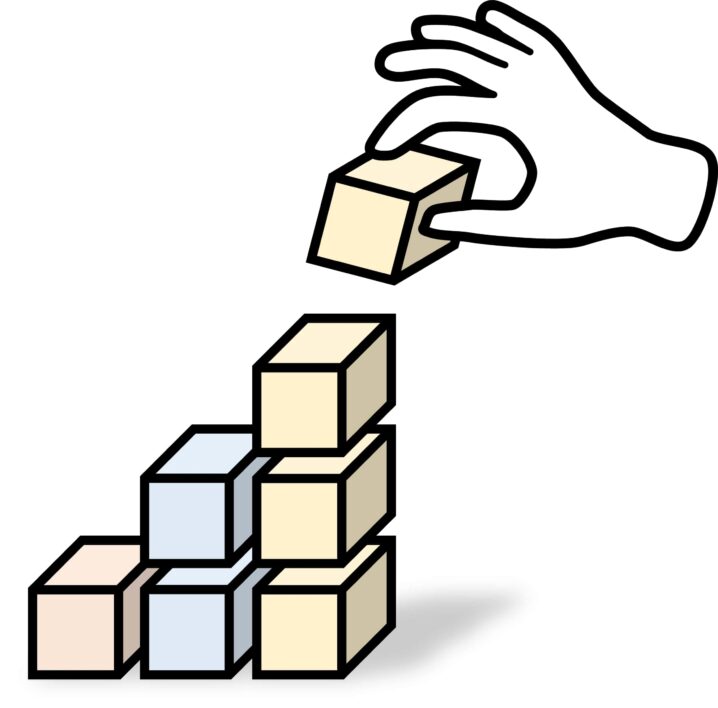








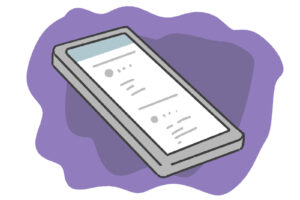


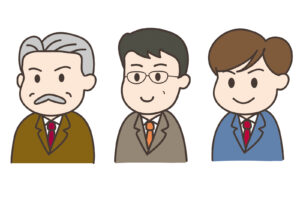

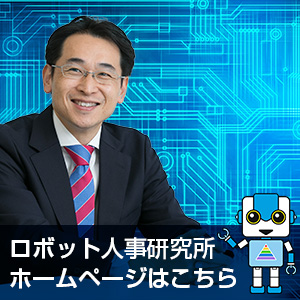
コメントを残す