先日、お客様の会社で、
営業部の社員さんと
エレベーターで一緒になった際、
こんなことを言われました。
「開発部が新しいプロジェクトを
進めているみたいですが、
あれって上手くいくんですか?」
この会社では、私は、毎年、
様々なプロジェクトのサポートをしています。
この社員さんとは、昨年、
プロジェクトを一緒に進めていましたが、
今年は、私が開発部のプロジェクトの
サポートに入っているため、
話す機会がありませんでした。
「開発部のプロジェクトをご存知なんですね!」
と私が答えると、彼はこう続けました。
「そりゃ、知ってますよ!
営業部にも影響のある話ですからね!
でも、営業部には何の話もないんですよ!」
彼が言いたいことは、
話は知っているけれど、正式に聞いていない
ということでした。
つまり、情報は入ってくるが、
正式なコミュニケーションルートが
機能していないということです。
そこで、私は、
「気になるんだったら、
教えて欲しいと言えばいいじゃないですか?」
と提案してみましたが、
彼は苦笑いするだけでした。
おそらく、正式に話がないと、
他部署のことを聞いてはいけない
という暗黙の雰囲気が
組織にあるのだと思いました。
なぜコミュニケーションが取れないのでしょうか?
それは、そっちから言うべきだ!という
思い込みがあるからです。
同じ会社なのに
どちらが先に言うべきか?を
気にしているのは、もったいないです。
気づいた人が行動すればよいのです。
今回の件に限らず、
一般的にそうできないのは、おそらく、
部門間の過度な配慮や
「こうあるべき」という思い込み、
失敗や批判を恐れる組織風土が
あるのだと思います。
これらの要因のために、
本来持っている能力が発揮できなく
なっているのです。
多くの組織で
心理的安全性の重要性が語られていますが、
「安全性を高めよう」と呼びかけるだけでは
心理的安全性は高まりません。
真の心理的安全性は、
明確な目的と目標の共有から生まれます。
【ビジョン】
何を目指しているのかが明確である
【ミッション】
何のためにやるのかが共有されている
【バリュー】
そのために何が大事かが共有されている
この3つの条件が揃って初めて、
本当の意味での
心理的安全性が生まれるのです。
「何としても目標を達成したい!」と
全員が強く思えるようになれば、
遠慮している場合ではありません。
目標達成に向けて、
やるべきことをやるだけです。
そうなっていれば、
今回のブログで書いたような
他部署の状況を聞けないという状況は、
なくなると思います。
コミュニケーションは大事なのですが、
その前提として、
ビジョン・ミッション・バリューが
共有されている必要があるのです。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
TB経営塾12期を開催します!
チームビルディング経営塾はこんな方におすすめです
◆社員を巻き込んで経営したいのにどうしてよいか分からない経営者の方
◆今いるメンバーでももっと成果が出せると思っているのに上手くいっていない経営者の方
◆人が辞めてしまう、人が育たないなど、人の問題で悩んでいる経営者の方
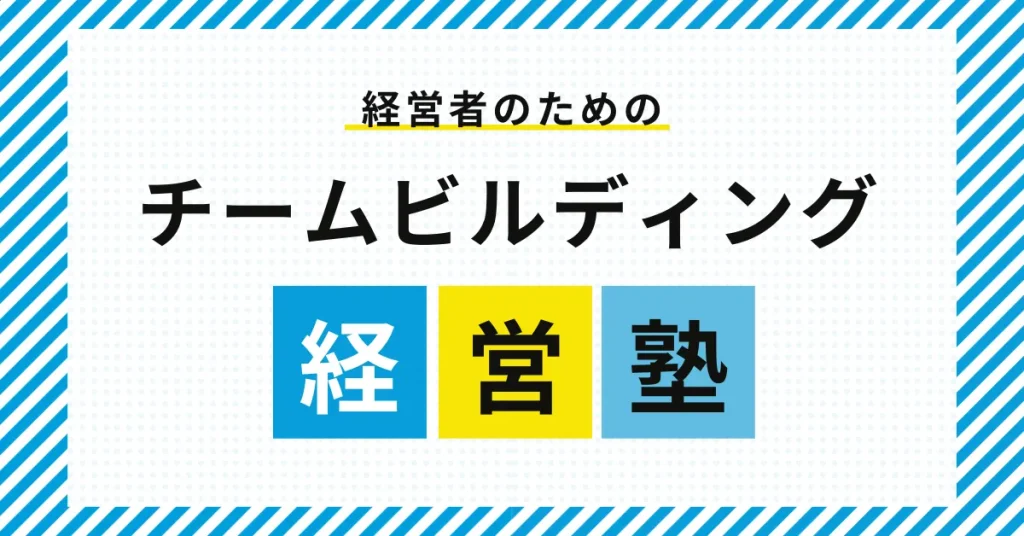
組織づくりのノウハウを
全6回の講座で学ぶことができます
チームビルディング経営塾の詳しいことはコチラ
https://robotjinji.co.jp/teambuilding_keieijuku-12
興味のある方はコチラにお問い合わせください!
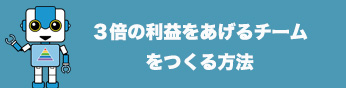


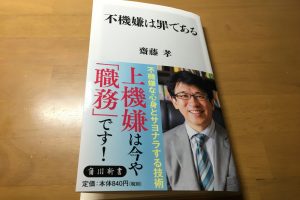

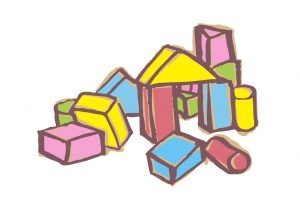

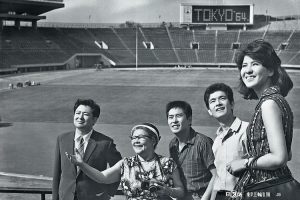
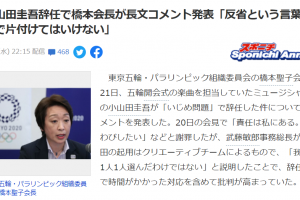

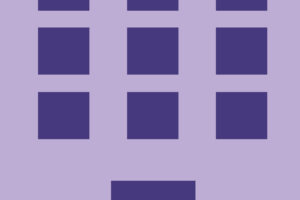


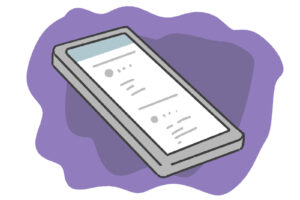

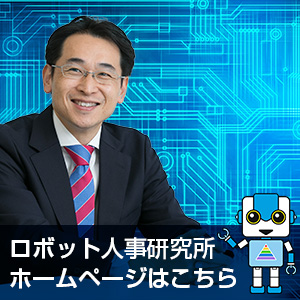
コメントを残す